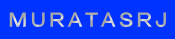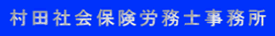労働法上における休日は、労働者が労働契約上、労働する義務を免除された日のことをいいます。暦日の0時からはじまる丸1日の休みが原則ですが、交代勤務等で暦日の休日付与が難しい場合、終業から起算して継続24時間の休みを与えることも可としています。
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(法定休日)(第1項)。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合(変形週休制)については、第1項の規定は適用しない(第2項)としています。
週あたり法定休日を超えた日数の休日を法定外休日とよび、法定休日とあわせて所定休日と呼んでいます。 この意味で週休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(土・日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致する必要はありません。
原則として、法定休日には労働させることはできませんが、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法第33条)や労働者の過半数の加入する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定(労働基準法第36条による協定。いわゆる三六協定)を締結、行政官庁に届け出ることにより法定休日に労働させることができます。
労働基準法にいう法定休日に労働者を働かせた場合には、使用者は3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。一方、法定以上に与えている休日(法定外休日)における労働は、休日労働とはならず、週あたりの法定労働時間を超過しない限り、賃金に割増を加算しなくともよく、日または週あたりの法定労働時間を超過してはじめて、時間外労働として2割5分増しの割増賃金が発生するにすぎません。逆に休日割増が付加される休日労働とした日の勤務は何時間働いても、時間外労働の対象とはなりませんし、週の法定労働時間の算定にも加わりません。
また、労働基準法にいう休日とは別に、法令に従い年次有給休暇を与えなければなりません。労働義務のある日を労働者が休むことを「休暇」といい、使用者が与える休日とは区別します。前勤務日の終了までに休日と労働日を入れ替えることを休日の振替と言います。休日から労働日となった日の労働については休日労働の割増の対象になりませんが、週あたりの法定労働時間を超過した時間については時間外労働となり、割増が発生することがあります。この手続をせずに労働させた場合、休日出勤として割増対象になり他の労働日を代休として与えても、割増の支払を免れられません。代休は使用者が、または労働者が日を指定して労働を免除する(される)ことです。ただし代休は必ずしも与えなくてもよく、代休の賃金は就業規則等に定めるところによります。